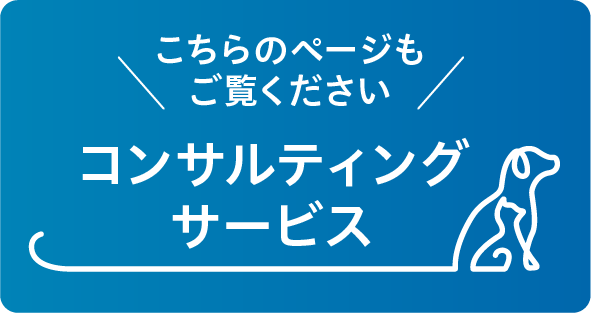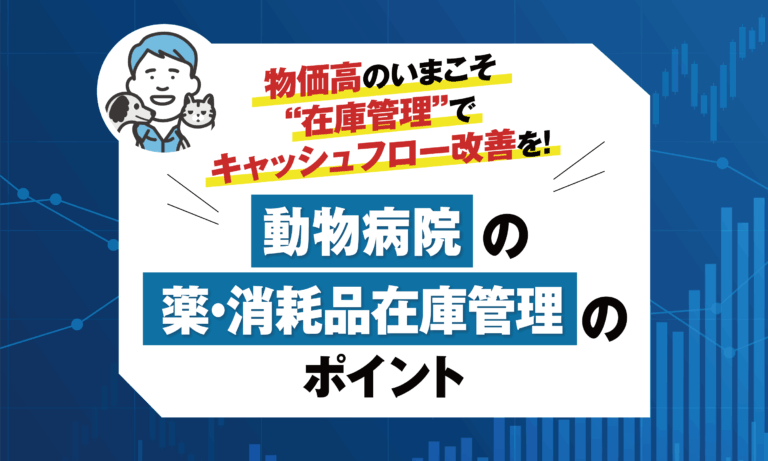
物価高が続くなか、動物病院の「薬や消耗品」のコストもじわじわと上がっています。従来のやり方のまま仕入れや在庫管理をしていると、知らず知らずのうちに利益が圧迫されてしまう時代に入りました。そこで今回は「仕入れ・在庫管理」から経営改善につなげる視点を解説します。“コストを抑えつつ、現場の質は落とさない”ためのヒントを、ぜひ参考にしてください。
(筆者紹介)
PEACE Lab 代表、獣医師 椿 直哉
2004年に獣医師免許を取得し、北里大学を卒業。企業動物病院の院長や、センター病院の立ち上げ・運営を経験し、17年にMBAを取得した。21年に独立してPEACE Labを設立し、現在に至る。猫専門クリニックや訪問診療などさまざまな形態の獣医療サービスを運営している。
物価高で“消耗品コスト”が経営を圧迫

近年の物価高を背景に、動物病院でも薬や消耗品の仕入れコストが大きく上昇しています。「以前と同じ感覚」で仕入れや在庫管理を続けていると、気づかぬうちに利益率が低下してしまうケースが増えてきました。
動物病院業界は自由診療であるため、原価や価格設定への意識が薄くなりがちな傾向があります。また、「かつての仕入れ先との関係性で買い続けている」「現場スタッフ任せになっている」といった状況もよく見受けられます。
近年ではEC化が進み、価格比較やスピーディな発注が可能になった一方で、逆に「どこで何を買えばいいのか」が複雑化している側面もあります。
そして発注ミスによる在庫過多や期限切れ、適正でない価格での仕入れが、“見えないコスト”として利益を圧迫しているケースは少なくありません。
私自身、「棚卸しの頻度を上げる」「発注ルートを整理する」といった取り組みだけで、キャッシュフローが大きく改善した事例をこれまでに何度も見てきました。
現金化できない在庫が院内に溜まることはリスクそのものです。まずは「現在の仕入れ・在庫管理に理由があるか?」を振り返り、数字を意識する文化を院内に根づかせる。それが、利益を守り、スタッフの働きやすさを向上させる第一歩になるのではないでしょうか。
「原価意識」の薄さが、知らぬ間に利益を削っていく

多くの院長先生は「獣医師」としての仕事に力を注いでこられた一方、経営者としての原価意識が十分に育っていないケースが少なくありません。とくに薬や消耗品の原価について、「昨年、いくら仕入れて、売上の何%を占めていたのか」と即答できる先生はごく少数です。勤務医時代に経営数字に触れる機会が乏しく、開業後に初めて経営の壁に直面する——これは業界全体の構造的な課題ともいえるでしょう。
さらに、多くの個人病院では「他院との比較情報」が得にくいため、自院の原価率や利益率が適正かどうかを判断しにくいという現実もあります。大手グループ病院であれば“横比較”が可能ですが、ホームドクター型の個人病院では「これくらいで大丈夫かな」という感覚頼みになりがちです。
加えて、近年は仕入れの流通も大きく変化しています。従来は「付き合いのある営業担当から買う」スタイルが主流でしたが、いまや EC化が進み、価格競争が激化しています。同じ製品でも価格差が大きく、発注先の選択一つで コストに大きな差が出る時代です。だからこそ、今こそ 「なぜこのルートから買っているのか」「価格に見合った価値があるのか」を見直すべき時期に来ています。
獣医療の質を保ちながら、適正な価格で仕入れること。それは “コストカット”ではなく、“経営品質の向上”に直結するはずです。
見えないコストが利益を蝕む——在庫管理・業務フローの盲点

消耗品や医薬品の仕入れにおいて、“見えないコスト”が院内に潜んでいるケースは意外と多いものです。たとえば、次のような事例がよく見られます。
- 欠品による二重発注や在庫過多
-
必要なタイミングで在庫がなく、慌てて注文 → 数日後、もう一度発注 → 同じ商品が重複して届く……。こうして余剰在庫が積み上がり、使用期限切れ・滅菌期限切れといった“死蔵コスト”が発生することも珍しくありません。
- 処方業務にかかる“隠れ人件費”
-
処方・調剤に手間がかかる薬剤を扱うことで、1件につき数十分かかってしまうことがあります。例えば複数剤の分包や長期処方で、30分ほどかかるケースも。1回あたり500円程度の調剤料しか取っていない場合、明らかに赤字労働になっているのです。
- 割高な薬剤を漫然と継続使用
-
ECの普及により、同一成分でも価格差が大きくなっているにもかかわらず、旧来のルートから割高な薬を漫然と仕入れているケースは多々あります。また、発注ルートやルールが整備されていないことで、スタッフごとに発注先がバラバラになり、最適価格での仕入れが実現できていない病院も少なくありません。
これらの「見えないコスト」が積もり積もると、利益を大きく圧迫してしまいます。しかも、こうしたムダは「診療の質を落とさずに改善できる」ものばかり。まずは院内の在庫管理と業務フローを見直し、“利益を守る”仕組みづくりに着手してみてはいかがでしょうか。
棚卸しと発注ルートの見直しでキャッシュフローが改善

消耗品や医薬品の管理が徹底されていない動物病院は少なくありません。では、そこを見直すことでどんな変化が起きるのか——。
実際に、棚卸しの頻度を上げたことで、キャッシュフローが改善した病院は多くあります。なぜなら、在庫はあくまで“現金がモノに変わった状態”であり、現金化できない在庫が院内に積もれば積もるほど、経営の柔軟性が奪われていくからです。
たとえば、まとめ買いで倉庫に積み上がった薬や消耗品などの在庫。これは帳簿上は「資産」でも、給与や家賃などの支払いには使えない現金固定化の原因になります。これを「在庫」ならぬ「罪子」と呼ぶ人もいるほど、リスクを伴うのです。
また、発注ルートを整理するだけで仕入れコストが大幅に改善した例もあります。発注先を「薬はここ、消耗品はここ」と院内で統一することにより、価格比較が容易になり、仕入れ単価が最適化されました。
逆に、発注ルールが曖昧だと、頼まれたスタッフが「どこから買っていいかわからない」「高いルートで購入してしまう」「規格違いの商品を誤発注してしまう」など、余計なコストが発生する原因になります。 地道な取り組みですが、棚卸しの見える化と発注ルートの整備は、確実に利益を守る武器になります。
まずは、自院の「いま」を把握することから

「うちは問題ないはず」「そんなに原価はかかっていない」——。そう思っている院長先生ほど、実は現状が見えていないケースが多くあります。まずは、在庫の金額や仕入れ金額がきちんと把握できているか、確認してみてください。
次に、発注ルートや仕入れルールがスタッフ間で共有されているか、見直してみましょう。
発注業務は担当者の腕の見せ所ですから、協力を得られるようにする工夫も必要です。場合によっては、愛玩動物看護師でなく、パートの事務スタッフに任せる手もあるでしょう。
さらに、価格改定や原価上昇が、診療報酬(料金設定)に適切に反映されているかも重要なポイントです。仕入れ価格が上がっているのに料金は据え置きのまま——そんな状況では、知らず知らずのうちに利益が圧迫されてしまいます。
小さな改善の積み重ねが、経営の安定につながります。だからこそ、今こそ一度立ち止まって、「仕入れと在庫」の見直しに取り組んでみてください。
「コストの見直し」は決して“ケチる”ことではありません。病院の質を落とさず、利益と時間を生み出すための前向きな取り組みです。
もし、「自院はどうなんだろう?」「どこから手をつければいい?」と思ったら——
ぜひ一度、PEACE Labにご相談ください。
月商や仕入れ状況をもとに、改善ポイントのアドバイスも可能です。“ムダを減らし、未来に投資できる病院”を一緒に目指していきましょう。