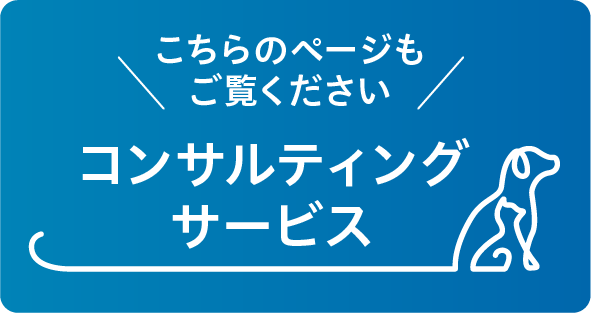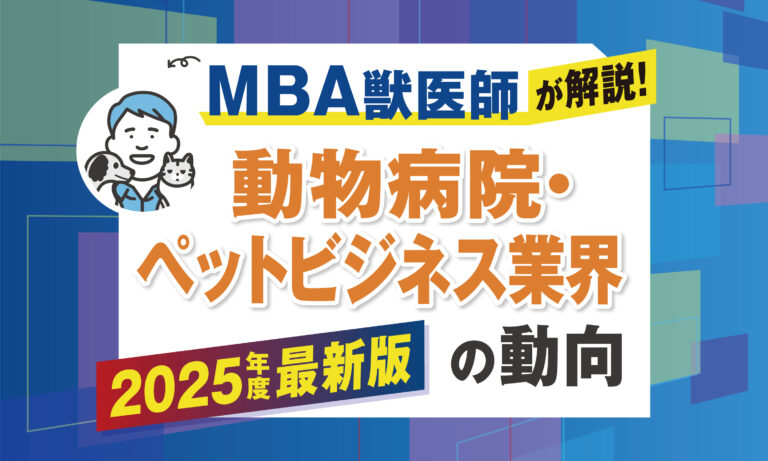
動物病院関係者やペット関連企業の皆さんにとっても、そろそろ年度初めの慌ただしさも落ち着いてきた頃ではないでしょうか。現在の立ち位置を見直し、次の一歩を考えるにはちょうど良いタイミングです。そこで今回は、動物病院業界の今後のトレンドになるであろうトピックスを4つご紹介したいと思います。
(筆者紹介)
PEACE Lab 代表、獣医師 椿 直哉
2004年に獣医師免許を取得し、北里大学を卒業。企業動物病院の院長や、センター病院の立ち上げ・運営を経験し、17年にMBAを取得した。21年に独立してPEACE Labを設立し、現在に至る。猫専門クリニックや夜間救急病院、訪問診療などさまざまな形態の獣医療サービスを運営している。
都市部では“設備投資型”の二次診療が進む

いま都市部では、「CT・MRIを備えた大型施設を新設する」という動きが加速しています。背景にあるのは、東京を中心とした人口の増加です。人が増えれば当然、動物を飼う世帯も増える。その結果、動物病院のニーズも「より高度な検査・治療を受けたい」という方向にシフトしています。
そうしたニーズを見越して、大手資本が1.5次〜2次診療を担う新たな動物病院を次々と開設しており、企業動物病院や高度医療動物病院からの人材の引き抜きも活発になってきています。
私は「都市部=飽和市場」だと思っていた時期もありました。しかし2次診療の分野に限っては、まだまだ“受け皿”が足りていないのが現状です。実際、既存の2次診療施設はどこも予約が取りづらく、紹介先に困っている1次診療の先生も多いはずです。
いま2次診療領域は、「開業すれば流行る」という非常に珍しいフェーズにあります。ですから大手資本が動くのも当然の流れだと思います。
ただし、だからといって個人病院が設備投資をして2次診療に参入するのが良いかというと、それは慎重に考えるべきでしょう。莫大な初期投資と、スタッフの採用・教育体制が必要ですし、相応のプレッシャーも伴います。
むしろ、自院の診療体制を見直しながら、周囲の2次診療施設とうまく連携する。その方が無理のない形で、患者さまと向き合い続けられるのではないかと感じています。
診療科目の明示が可能に。広告は「より正確に」「より誠実に」

2024年4月、獣医師法が改正され、広告に関する制限が大きく見直されました。
それまでは、動物病院の看板に「眼科」「外科」「皮膚科」など診療科目を明示することは基本的に認められていませんでした。もちろん、ホームページなどでは従来から記載されていましたが、これらは“広告”としては扱われていなかったためです。
しかし法改正によって、診療科目を正式に表示してよいことになりました。つまり、自院がどんな診療を得意としているかを、より正確に、より誠実に伝えるチャンスが増えたということです。
とはいえ、この「緩和」は同時に、情報発信における責任がより明確になったことも意味します。たとえば、比較広告や誇大表現は禁止のままです。「うちの治療なら必ず治る」といった表現や、「初診無料」「近隣より安い」といった訴求はNGとされています。SNSなどでの発信も含め、これまで曖昧だった領域が“白か黒か”に整理されたと言えるでしょう。
いまの段階では、制度の全容を掴みきれていない開業医の方も多いように思います。ただ、専門医や認定医といった公的な資格は、きちんと外に出していくべきですし、地域に向けて「こんな診療をしています」と発信していくことが、今後ますます重要になります。
それが過剰な売り込みでなく、患者さんの安心につながるのであれば、適切な情報発信はむしろ歓迎されるものです。いまこそ“まっとうな広告”について、院内でも一度見直してみるタイミングかもしれません。
初診からのオンライン診療が現実に? いま注視すべき制度動向

2024年12月、農林水産省からオンライン診療に関する新たな指針が示されました。これまで再診に限られていたオンライン診療が、将来的には初診から可能になるかもしれないという流れが出てきています。
すでに再診に特化したオンライン診療サービスを提供する企業も登場していますが、今後は予防医療や慢性疾患の診療をオンラインで完結させる動きが加速するかもしれません。
仮に、初診からの診療や予防薬の処方が認められるようになると、都市・地方を問わず、いままでローカルビジネスとして成立していた動物病院の経営環境が大きく変わる可能性があります。大手がプラットフォームを立ち上げ、獣医師を集めてオンライン上で診療する仕組みができれば、従来の1.5次診療や予防医療の分野が侵食されていくことも想定されます。
もちろん、オンライン診療では対応できないことも多くあります。実際に触って診る、検体を採取する、精密検査を行う——こうしたリアルな医療行為は不可欠です。ですから、これからの小規模病院には「リアルでしかできない価値」をどう高めていくかが問われます。
同時に、予防薬や慢性薬の処方といった“繰り返しの処方業務”がオンラインに取られると、それだけで大きな収益減になる恐れもあります。制度がどう整備されていくかを注視しつつ、いまできる準備をしておくことが大切です。
人口減少地域の開業に、思わぬチャンスも

都市部では競争が激しくなる一方で、地方では別の課題が浮上しています。それが「動物病院そのものの数が減っている」という現状です。高齢の院長先生が引退し、後継者がいないまま閉院していく——そんなケースが少しずつ増えています。
一方で、こうした地域で新たに開業した動物病院が“想定以上に繁盛している”という話も耳にします。周辺に競合が少ないため、いわば“地域の一極”として機能することができるのです。
もちろん、人口が減っている地域ですから、ペットの飼育頭数も右肩下がりかもしれません。ただ、それでも一定のニーズが残っている地域は確実に存在しています。既存の病院がなくなれば、飼い主さまは新しいかかりつけを必要とします。
私自身、「地方だから厳しい」という見方をしていましたが、むしろ“戦略的な開業先”として見直す価値はあるのではないかと感じています。しっかりと市場調査をしたうえで、競合の少ない地域に入り、地域の飼い主さまに寄り添う形で診療を続ける。そんな形の開業スタイルが、これからは増えていくかもしれません。
まとめ:「二年後の自院」がどうなっているか、想像してみてください
いま業界では、都市と地方、リアルとオンライン、個人と資本——さまざまな対比のなかで、静かに地殻変動が起きています。
獣医療に関わるすべての方にとって、「いまどこにいて、これからどこを目指すのか」を考えるタイミングが来ているように思います。いま何も動かなくても、変化の波は確実にやってきます。そのとき、自分がどのような立ち位置にいたいかを、いまのうちから想像しておく。そうすることで、いざというときの判断に迷わなくなると思うのです。
PEACE Labでは、動物病院を経営する獣医師の皆さまの立場に寄り添いながら、これからの選択を一緒に考えるコンサルティングを行っています。時代の流れを読み解き、最適な一歩をともに見つけていきましょう。